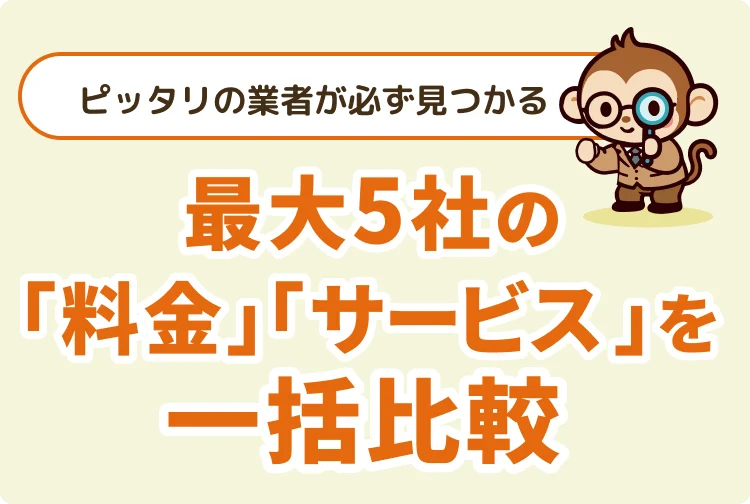空き家問題と田舎の実家じまい|ゴミ屋敷の処分はどうする?

- 空き家問題は深刻化している
- 放置は危険!空き家がもたらすリスクとは?
- 全国で増える「実家ゴミ屋敷」問題!
- 実家を空き家のまま放置するとどうなる?
- 何から始めればいい?実家じまいの手順
- 田舎の実家じまいのリアルな課題
- ケース別|おすすめの実家じまいの進め方
- 費用負担を軽減する制度を活用しよう
- 空き家対策!田舎の実家が売れないときの対処法
- まとめ
- 高齢化による体力の低下
「重い物を動かせない」「ゴミ出しが負担になる」など、体力の低下が影響することもあります。 - 「もったいない」意識が強い
まだ使えるからゴミではないと、なかなか処分に踏み切れないことも。 - 病気・認知機能の変化
「同じ物を何度も買ってしまう」など、認知機能の低下などで、モノが増えていき結果ゴミ屋敷となってしまうケースも。 - 同居しておらず、今後も住む予定がない
- 実家に定期的に帰省できていない
- ご近所との付き合いが薄れてきた
- 少量の場合
持ち帰って自宅の自治体で処分 - 大量の場合
直接処理場へ持ち込む、または不用品回収業者を利用 - 地域トラブル回避
事前にご近所への挨拶回りを行い、理解を得てからゴミ出しをする
実家じまいを検討するタイミングは人それぞれです。
親の高齢化や施設入居、ご自身の終活をきっかけに、「誰も住まなくなった田舎の実家をどうすればいいのか」と悩まれる方は少なくありません。
特に遠方に実家がある場合は、空き家の管理や今後の対応に頭を抱えることも多いでしょう。「子どもたちに負担をかけたくない」と考える親御さんもいるかもしれません。
この記事では、そうした田舎の実家じまいにまつわる具体的な課題に焦点を当て、その解決策や安心して進めるための知識をわかりやすく解説していきます。
片付けのコツや費用の目安、地域ならではの注意点、トラブルを避けるポイントまで、幅広くご紹介します。
実家じまいに不安を感じている方の、第一歩を踏み出す手助けとなれば幸いです。
空き家問題は深刻化している
日本では現在、空き家問題が深刻な社会課題となっています。
総務省の2023年度調査によると、全国の空き家数は約900万戸に達し、住宅総数に占める割合は13.8%にも上ります。この数字は年々増加傾向にあり深刻化が顕著です。
田舎だけじゃない!都心部でも課題に
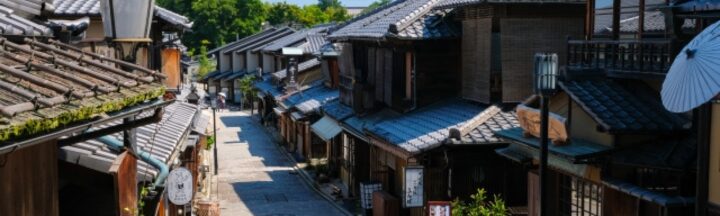
京都市をはじめとする都心部でも、空き家対策に関する条例が制定されるなど、問題は全国に広がっています。
都心か田舎かにかかわらず、実家が遠方にある場合は「実家じまい」が難しくなり、そのまま空き家になってしまうケースも少なくありません。
ただし、住みやすさや利便性の面で土地の売却が難しい田舎では、より深刻な空き家問題を抱えているのが現状です。
放置は危険!空き家がもたらすリスクとは?

空き家を放置することには、さまざまなリスクが潜んでいます。
空き家が招く3つのトラブル
建物の劣化による安全リスク
人が住まなくなった建物は、想像以上に早いペースで劣化が進みます。屋根の破損、外壁のひび割れ、基礎の沈下など、構造的な問題が発生し、最悪の場合は建物の一部が崩れ落ちて通行人にけがを負わせる可能性もあります。
治安の悪化
管理されていない空き家は、犯罪者や不審者が住み着いたり、犯罪の拠点として利用されるリスクが高まります。また、ごみの不法投棄の温床となることも多く、地域の治安悪化につながります。
近隣への迷惑
雑草の繁茂、害虫・害獣の発生、悪臭の発生など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼします。
実際に「近くの空き家に鳩が住み着いて、鳥が苦手なのでとても迷惑」という声も聞かれます。
全国で増える「実家ゴミ屋敷」問題!

特に深刻なのが、長年住み続けた実家に家財道具が蓄積し、結果として実家が“ゴミ屋敷”のようになってしまうケースです。
物の量があまりに多く、ご自身では手がつけられなくなってしまうことも少なくありません。
さらに、親世代が亡くなった後に相続人が片付けを引き継ぎ、処分に困るケースも急増しています。
なぜゴミ屋敷になってしまう?
実家がゴミ屋敷になってしまう理由は、だらしなさや性格の問題ではありません。
多くの場合、いくつもの要因が重なって起こります。
実家がゴミ屋敷になるかも|こんな人は要注意!
以下の条件に当てはまる方は、実家のゴミ屋敷化が進行していても気づきにくい傾向があります。
このように、遠方に住んでいて帰省の頻度が低いなど、実家や地域との関わりが少なくなると、家の中の変化に気づきにくくなります。
その結果、気づいたときにはすでに手が付けられない状態になっていることも少なくありません。
上記に当てはまる方は、意識的に実家の様子を確認するなど、早めの見守りや声かけを心がけることをおすすめします。
実家がゴミ屋敷になってしまった際の対処法
ゴミ屋敷になってしまった実家の片付けは、ごみの多さだけでなく、害虫や害獣が住みついているなど、衛生面の問題が発生していることもあります。
このような状況では、自力での片付けは非常に困難です。
不用品回収業者や専門の片付けサービスを活用することで、安全かつスムーズに実家じまいを進めることができます。
リユース相談本舗では「ゴミ屋敷の片付け」に関するご相談を承っております。
「自分ではどう片付けていいのかわからない」「どこに頼めばいいのか不安」——そんなお悩みを抱えている方は少なくありません。
リユース相談本舗は店舗を構えているため「対面でのご相談」が可能です。もちろんお電話や問い合わせフォームからのご相談も受け付けております。
ゴミ屋敷の片付けについて少しでも不安なことがある方は、まずは完全無料の相談カウンターでお気軽にご相談ください。
>>相談カウンターで相談する
実家を空き家のまま放置するとどうなる?
空き家を放置することで発生する問題は、経済面から社会面まで多岐にわたります。
継続的な費用負担がかかる
| 名目 | 費用 | 回数 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 5万円〜数十万円 | 年1回 |
| 光熱費 | 2千円〜1万円 | 月1回 |
| 火災保険料 | 1万円〜10万円 | 年1回 |
| 建物の清掃補修 | 数万円〜数十万円 | 数年に1回 |
| 庭木の手入れ | 5千円〜5万円 | 年2回程度 |
| 共益費・管理費 | 5千円〜2万円 | 月1回 |
このように空き家を管理するだけで、年間すると少なくない費用がかかっていることがわかります。
税制優遇制度を受けられない
空き家となった実家を売却する際、相続から3年以内に売却するなど、条件次第では最大3,000万円の特別控除を受けることができます。
この期間を過ぎると控除を受けられなくなり、大きな税負担が発生する可能性があります。
物件価値が下落しやすい
建物は人が住まなくなると、住んでいたころよりも早いペースで経年劣化が進みます。
長く空き家のまま放置することで、売却時の価格が大幅に下がる可能性があり、売れるものも売れなくなってしまう可能性もあります。
実家じまいをすることで、これらのデメリットはメリットに変わります!ぜひ一度、実家じまいを検討してみましょう。
何から始めればいい?実家じまいの手順
空き家のまま放置してしまうと、老朽化や近隣トラブル、税制上の不利益など、さまざまなリスクが生じることをご紹介してきました。
だからこそ、「実家をどうするか」を早い段階で決め、具体的に行動に移すことです。
とはいえ、いざ実家じまいをしようと思っても、「何から始めればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
ここからは、実家じまいをスムーズに進めるための基本的な手順を、わかりやすくご紹介します。
1.家族と相談して方針を決める

まずは、相続人や関係者全員で話し合い、実家を今後どうするかの方向性を決めましょう。
売却・賃貸・解体・保有など、選択肢を整理したうえで、予算や時期も含めた合意を得ておくことが大切です。
2. 残す物・処分する物の仕分け

家の中の家財道具を「残すもの」「処分するもの」「判断保留」の3つに分類します。
現金・貴金属・権利証・重要書類などの貴重品は、早い段階で確認しておきましょう。
仕分けの過程で、家族の思い出話に花が咲くことも多く、時間に余裕をもって取り組むのが理想です。
3.不用品回収や粗大ごみで処分
燃えるごみで処分できないアイテムは、自治体の粗大ごみを依頼する、または大量の不用品が出る場合は、不用品回収業者の利用がおすすめです。
※横にスクロールできます| 項目 | 自治体の粗大ごみ回収 | 不用品回収業者 |
|---|---|---|
| 処分費用の目安 | 1点300〜2,000円前後 | 軽トラ1台分:1.5〜3万円 2tトラック1台分:5〜10万円程度 |
| 搬出作業 | 指定場所まで原則自己搬出 | 業者が運び出し含むすべて対応 |
| メリット | 費用が安い | ・一度に大量に処分できる ・高齢者や遠方の場合に便利 |
建物の解体を予定している場合は、家財を含めてまとめて処分する方法もあります。
また、自治体によっては解体費用や処分費用に補助金が出る場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
仏壇や位牌など宗教的な意味合いをもつ品は、一般のごみとして捨てるのではなく、適切な供養を手配する必要があります。
<PR>リユース相談本舗は、実家じまいや仏壇処分など、暮らしの中で気になるお片付けや整理のご相談ができる買取店です。対面でお客様の声を伺いながら、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
店内には、経験と知識が豊富な目利きアドバイザーが在籍しており、ご自宅に眠っている不用品の中から思わぬ価値を見つけるお手伝いをさせていただきます。
まずは、相談無料の店舗型相談カウンターで少しの不安や疑問でも一緒に解決していきましょう。
>>リユース相談本舗の相談カウンターはこちら
4.清掃・売却・空き家管理の手配

建物を賃貸に出す場合は、ハウスクリーニングなどを行い、見た目や衛生面を整えておくことが必要です。
売却が難しい場合や、しばらく利用予定がない場合は、「空き家バンク」や「空き家管理サービス」を活用する選択肢もあります。
田舎の実家じまいのリアルな課題
田舎の実家じまいには、都市部にはない特有のハードルがあります。
片付けがとにかく大変

費用と時間の負担
遠方にある実家に通う場合、往復の交通費だけで数万円、宿泊費も含めると一回の訪問で5〜10万円程度かかることもあります。
物が多い場合は複数回通う必要があり、総額で数十万円になるケースもあります。
また、長年住み慣れた家や思い出の詰まった品物を処分することへの寂しさや罪悪感から、なかなか片付けが進まないケースも。
作業期間の長期化
田舎の家は面積が広く、物置・納屋・蔵があることも多いため、家財の量も膨大になりがちです。片付けに1〜3ヶ月以上かかることも珍しくありません。
中にはゴミ屋敷に近い状態になっている実家もあり、片付けの負担は非常に大きくなります。
これが実家じまいが滞る一つの要因にもなっています。
ご近所とごみ問題

実家じまいでは、大量のごみが出ることは珍しいことではありません。その際、ごみの出し方にも注意が必要なケースがあります。
ごみ出しのハードル
田舎では、ごみ捨て場を町内会で管理していることも多く、町内会費の未納や掃除当番の不参加が理由で、実家の持ち主がごみを出しづらい状況になることがあります。
また、自治体によっては指定のゴミ袋が必要であったり、一度に出せるごみの量が決まっている場合があります。
大阪市では3袋程度を目安としており、東京都では区によって異なりますが、多くの地域で3袋以内とされ、4袋以上は有料になる区もあります。実家のある自治体のルールを事前に確認しておくことが大切です。
地域とのコミュニケーション不足
田舎はご近所付き合いが密な分、地域と疎遠になっているとトラブルに発展することも。
久しぶりに帰省してごみを大量に出した場合、心象が悪くなるケースもあります。
ごみ捨ての対策方法
こういった大変さを緩和させるためにも、若く元気なうちに実家じまいを検討しましょう。
少しずつ始めていくことで、ご自身の死後に、残されたご家族の負担を軽減することが可能です。
田舎の実家じまいだからこそ必要なマナー
都会と違って近所との関係性が密接な田舎では、実家じまいにも特別な配慮が必要です。
近隣への挨拶回り
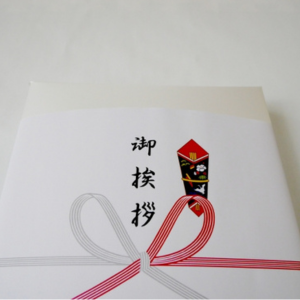
実家じまいを始める前には、必ず近隣の方々への挨拶回りを行いましょう。「長い間お世話になりました」という感謝の気持ちを伝えることで、作業への理解も得やすくなります。
田舎の実家ならではエピソードも
挨拶に伺うと、「あなたが小さい頃によく遊びに来ていたわね」「お父さんとはよく一緒に畑仕事をしたのよ」など、昔の思い出話に花が咲くことも多くあります。
こうした交流は、実家じまいの重い気持ちを少し軽くしてくれる貴重な時間でもあります。
地域への最後の貢献
可能であれば、まだ使える家財道具を地域の方に差し上げたり、地域の施設に寄付したりすることで、最後に地域への恩返しができます。
ケース別|おすすめの実家じまいの進め方
実家が近場にある場合のおすすめ方法
実家が近くにある方で、時間や体力にある程度余裕がある場合は、自分で片付けを進めて、処分費用を抑える方法がおすすめです。
日用品や衣類などは可燃ごみや粗大ごみとして自治体のルールに従って処分し、大型家具や家電などは不用品回収業者に依頼することで、コストを抑えながら無理なく進められます。
ただし、想像以上に時間と体力を要するため、ご自身のスケジュールや体力にどれだけ余裕があるかを客観的に見ながら計画を立てることが大切です。
実家が遠方にある場合のおすすめ方法
実家が遠方にある方や、頻繁に足を運べない場合は、一括で片付けを任せられる不用品回収業者の利用がおすすめです。
最初に、貴重品や残しておきたいものをしっかりと選別しておき、その後は業者に依頼して一気に作業を進めるとスムーズです。
また、買取サービスを兼ねた業者を選ぶことで、自分では気づかなかった価値のある品を査定・買取してもらえる可能性があります。
初期費用はかかるものの、交通費・宿泊費・移動にかかる時間的コストを考えると、結果的に効率的で現実的な方法といえるでしょう。
費用負担を軽減する制度を活用しよう
自治体によっては、実家じまいに適用できそうな補助金制度を設けている場合があります。
空き家解体費用の補助金
多くの自治体で老朽化した建物の解体費用に対する補助金制度があります。補助額は工事費の半額(上限50〜100万円程度)が一般的です。
ブロック塀撤去の補助金
ブロック塀の撤去に対する補助金制度も設けられている自治体があります。
空き家対策!田舎の実家が売れないときの対処法
田舎の実家を売ろうとしても、なかなか買い手が見つからないというケースは少なくありません。
ここでは、そんな「売れない実家」に対して取れる現実的な対処法を解説します。
解体して更地にする

建物が老朽化している場合は、思い切って解体し、更地にすることで買い手が見つかりやすくなるケースがあります。
特に、土地の利用を目的とする購入者や企業にとっては、更地の方が扱いやすく、売却のハードルが下がる可能性があります。
ただし、固定資産税が増額される場合があるほか、解体後も売れなかった場合には費用だけが残るリスクもあります。解体にかかる費用や売却見込みを踏まえて、慎重に判断することが大切です。
空き家バンク・管理サービスを活用する
空き家バンクとは
国や自治体が運営する「空き家バンク」も有効な選択肢です。空き家バンクとは地域への移住希望者や若年世帯とのマッチングを目的とした制度で、売却だけでなく、賃貸としての登録も可能です。買い手が見つかりにくい物件でも、新たな活用の機会につながる可能性があります。
空き家管理サービスとは
定期的な巡回・換気・庭木の手入れなどを代行してくれるサービスとなっており、物件の劣化や近隣トラブルを防ぎつつ、資産価値を維持できます。
すぐには手放せない、あるいは将来の活用を視野に入れている場合は、空き家管理サービスの利用がおすすめです。
まとめ
田舎の実家じまいは、都市部とは異なる様々な課題がありますが、適切な手順と準備で解決可能です。重要なのは早めの決断と行動です。空き家問題は放置するほど解決が困難になり、費用も膨らみがちです。
実家じまいに困った際は、経験豊富な専門業者に相談することをおすすめします。
一人で抱え込まず、適切なサポートを受けながら、思い出の詰まった実家に感謝の気持ちを込めて、適切な形で最後のお別れをしましょう。