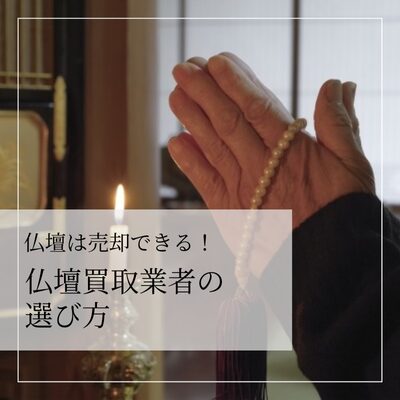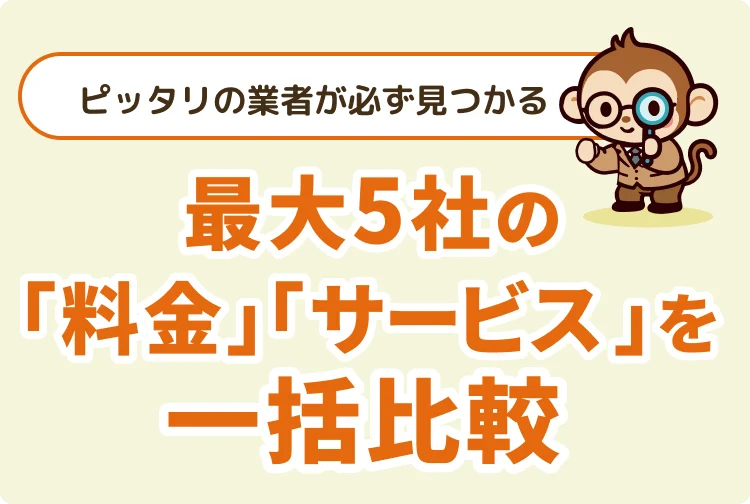エンディングノート(終活ノート)とは?書く内容と作り方の見本を紹介

- エンディングノートとは
- エンディングノート作り方
- エンディングノートを作成するコツ
- エンディングノートの内容と項目と書き方
- 大事な情報がつまったエンディングノートの保管は重要です
- 終活で身の回りを整理したいならリユース相談本舗へ
- エンディングノートと遺言書の違いが知りたい人
- エンディングノートに書く内容を知りたい人
- エンディングノートの作り方の見本を知りたい人
- 市販のエンディングノートを購入して書く
- 一般的なノートやルーズリーフなどを使って自作する
- パソコンを使ってWordやGoogleドキュメントで作成
- 基本的な個人情報(本籍地、家族構成など)
- 財産・資産について
- ネットサービスなどのIDやパスワード情報
- 医療・介護の意思表示
- 葬儀・お墓についての意思表示
- 友人や知人、関係者リスト
- 家族や友人へのメッセージ
- 氏名
- 生年月日
- 血液型
- 本籍地
- 家族構成
- 趣味や好きなこと
- 銀行口座、証券口座の一覧作成
- 保険契約の内容確認
- 不動産の権利関係の整理
- 借金や保証債務の確認
- 相続税の試算
- SNSアカウント
- 写真や動画データ
- 仮想通貨
- オンラインサービスの契約
- クラウドストレージのデータ
- 危篤状態になった場合、延命治療を希望するか
- 介護が必要となった場合、家族介護を希望するか
- 末期の在宅治療を希望するか
- 死後、臓器提供を希望するか
- アレルギーや持病の有無、大きな病気の経歴など
- 葬儀の形式(一般葬、家族葬、直葬など)
- 葬儀社の選定と予算の希望
- 信仰する宗教・宗派
- 葬儀に呼ぶ人・呼ばない人
- 遺影に使う写真の希望
- お墓に関する希望
- 死後に連絡してほしい友人知人の名前
- 連絡先
- かんたんな自分との関係性
エンディングノート(終活ノート)は近年話題になっている終活の一環で、テレビや新聞などのメディアでも紹介される機会が増えました。存在自体は知っているけど具体的にどういったものかわからない方や、実際に書いてみたいけど書く内容が分からない方もいらっしゃるでしょう。
この記事ではエンディングノートの書き方や作り方、書く内容と注意点を解説します。
この記事はこんな人におすすめ
エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分の「人生の終わり」に向けて、家族や大切な人に伝えたい情報や希望を自分で記録するノートのことです。終活ノートと紹介されることもあります。
自分に万が一のことが起こった際に、家族や大切な人に契約している保険・銀行口座の種類・医療や介護についての意思表示・知らせてほしい友人のリストなどを書き残しておくものです。
エンディングノートには決まった形式があるわけではありません。
市販のノートを使っても作成できるため、気軽な気持ちで用意することができます。現在では書店での販売も見かけたり、インターネット上でフォーマットが配布されていることもありますので、自分が取り組みやすい方法ではじめてみるのが良いでしょう。
エンディングノートの必要性・メリット
エンディングノートの目的には、残された家族の負担を軽減すること・自分の意思や希望を残すことなどが挙げられます。
突然の病気や事故で亡くなった場合、家族は心の整理がつかないまま本人の意思を推測しながら重要な決断を迫られることになります。また、相続手続きや葬儀の準備、身の回りの整理など、遺族が行わなければならない作業は膨大です。
事前に終活を行うことで、これらの負担を大幅に減らし、家族が悲しみに集中できる環境を整えることができます。さらに、自分自身も人生の最期について考えることで、残りの人生をより充実して過ごすことができるでしょう。
エンディングノートはいつから作るべき?年齢は?

エンディングノートを作り始めるのはどんな年代の方でもOKです。何歳から作るべき、といったものはありません。
多くの人は高齢の方が行うことという認識があるため、「自分にはまだ早い」と考えてしまいがちですが、明日突然事故に遭う可能性はどんな年代の方にも等しくあります。
たとえ死亡してしまうような大きな事故ではなかったとしても、意思表示ができない状態、寝たきりの状態、失明や足腰の外傷によって思うように動けなくなってしまう場合も考えられます。こうしたことから早め早めの準備が必要であるといえるでしょう。そのため、大げさに聞こえるかもしれませんが、10代の方でもエンディングノートを準備しておくことをおすすめしています。
エンディングノートは遺言書と何が違うの?

エンディングノートは誰でも気軽に作成できる反面、法的効力はありません。あくまで自分の希望や思いを書き残しているノートだからです。もし、土地や財産といったしっかりとした資産をお持ちの方は、家族間トラブルを防ぐためにも法的効力のある遺言書を作成しておくとより安心です。
エンディングノートと遺言書の違いは法的効力があるかどうかが大きな違いとなりますが、その他の違いを表にまとめました。
| エンディングノート | 遺言書 | |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり |
| 書き方の自由度 | 自由 | 法律で定められた要件がある |
| 記載内容 | 自由 | 相続/財産の処分法/身分に関する事項(子の認知など) |
| 作成費用 | 0円(文房具代程度) | 弁護士全面サポートなら11万円~55万円目安 |
| 保管方法 | 自宅保管など | 法務局や公証役場での保管が望ましい。 |
| 作成目的 | 自分の希望や情報を家族に伝える | 死後の財産分配などについて法的に意思を示すため |
エンディングノート作り方
エンディングノートの書き方は自由であるため、どんな方法でも作成可能です。主な作成方法は以下の通りです。
市販のエンディングノートを購入して書く
エンディングノートは文房具メーカーなどから販売されています。Amazonなどで購入できるため、はじめてエンディングノートを作成する方にオススメです。
ただし注意点がいくつかあります。筆者はいくつか実際に購入して記入してみましたが、ネットで購入したものはエンディングノートの中身がわからず、自分に不必要な項目が多くあったり、書きたい項目の欄が足りなかったり、何年か経ってから記入内容を更新するとごちゃごちゃになってしまったりと、自分の思い通りにならないなと感じることがありました。(筆者が少し神経質な性格であるからともいえます)
市販のノートは書き方見本が付いていることが多いので、迷わずに書き進められることが大きなメリットではないでしょうか。
一般的に販売されているエンディングノート

コクヨ エンディングノート
もしもの時に役立つノート
大手文房具メーカーのコクヨさんから販売されているエンディングノート。CD-Rディスクを収納できるため思い出の写真データなども保管可能。

一番わかりやすい
エンディングノート
暗証番号などの重要情報を保護するスクラッチシールなどが付属しているため安心。専門的な解説もついているので、読み物としても利便性が高い。
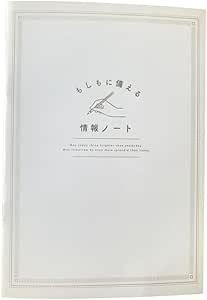
もしもに備える情報ノート
気軽に終活 エンディングノート
シンプルなエンディングノート。無駄な解説ページもなく、書き込みたいことをしっかり書き込めるので、後から読み返したり情報を更新したりするのに適しています。
一般的なノートやルーズリーフなどを使って自作する
市販のエンディングノートでは自分の書きたい項目がなかったり、欄が足りなかったり、不必要な項目が邪魔と感じてしまう方は、自分でエンディングノートを作ることをおすすめします。
一般的なノートでもOKですが、オススメしたいのは後から書き換えたり差し替えたりできるルーズリーフ型にすることです。
ルーズリーフ用のバインダーとそれに合ったサイズのルーズリーフリフィルを用意するだけで、後は自分の好きなように書きはじめられます。替えの利くルーズリーフですので、間違えてもOK。気軽に書けるのが魅力です。文房具屋さんはもちろんのこと、無印良品や100円ショップなどで購入できます。
パソコンを使ってWordやGoogleドキュメントで作成

自筆するのが面倒なかたはパソコンやタブレットなどを使ってWordやGoogleドキュメントというツールを使って作成する方法がおすすめです。
ノートやルーズリーフで作成するのと同じように自由度が高く、自分の必要な項目を書いていくだけでOKですので、比較的気楽に書き始めることが可能。
また、一から作成するのが面倒だと思う方はインターネットでエンディングノートのテンプレートを配布しているサービスもありますので探してみるとよいでしょう。よく知られているのは法務省のサイトやMicrosoftのサイトでしょうか。
印刷するだけで使えるフォーマットや、Word形式・Excel形式(スプレットシート形式)で、ダウンロードして自分でカスタマイズして使えるものなど様々な種類がありますので、気に入ったものを利用するとよいでしょう。このほとんどが無料で利用できます。
エンディングノートを作成するコツ
はじめは完璧を求めない
几帳面な人ほど陥りやすいのですが、エンディングノートはキレイに書こうとするとうまくいきません。
最初はキレイに書こうとしなくてOK。メモを残す感覚で書きましょう。
エンディングノートは何年か経った後に見直しをすることになりますので、その際に書き直すことを想定して気楽に書きましょう。
書きやすい項目からまとめていく
エンディングノートはどの順番で書いてもOK。そのため書きやすい項目からはじめてみましょう。
葬儀やお墓、医療関連など気持ち的に書きにくい項目は後回しにして、友人知人のリストや利用しているネットサービスのリストなどから始めると書きやすいでしょう。
家族と話し合いながら書いていく
資産の有無や医療・お墓について意思表示などは家族と話し合いながら書いていくとよいでしょう。
自分と家族の意思がかけ離れていないかを確認する目的や、残しておくべき項目に見落としがないかを確認する目的があります。
エンディングノートの内容と項目と書き方
エンディングノートに書くべき内容や順番に決まりはありませんが、書いておいたら役に立つことを紹介します。
1.基本的な個人情報(本籍地、家族構成など)
簡潔に自分のことをまとめて書いておきましょう。特に趣味や好きなことも書いておくと、後に家族が見た際に思い出話をしたり、認知症の症状などで要介護状態になった際に介護者が趣味や好きなことを把握する場合もあります。
個人情報記入のポイント
2.財産・資産について
財産・資産のリストと相続に関する意思表示を記しておきましょう。
資産の整理を行い、利用している銀行・不動産関係・証券・借金などをリスト化しておくことで相続時のトラブルを防ぎ、スムーズな手続きができるようにするためです。
財産の全体像が不明だと、相続人同士での争いや手続きの遅れが発生しやすくなります。
しっかりとした資産をお持ちの方や、家族以外に相続したいと考える方は混乱を避けるためにも遺言書の作成を検討してみましょう。
財産整理のポイント
3.ネットサービスなどのIDやパスワード情報
近年ではデジタル遺品と呼ばれがるものがあります。
故人が利用していたスマホ・パソコンのロック解除が出来なかったり、利用していたネットサービスがわからず解約手続きが出来ず支払い続けることになったり、SNSアカウントが放置されていることにより乗っ取りの被害にあったりと、様々なトラブルが想定されますので、利用しているサービスのリストを作っておき、IDやパスワードを家族がわかるように残しておくとよいでしょう。
デジタル終活のポイント
これらの情報をまとめておき、万が一の際には家族が代わりにログインして解約などの手続きを進められるようリスト化しておくことが大切です。
ただし、パスワードをそのままエンディングノートに記載するのは危険が伴うので、家族だけがわかるように工夫しておくことをおすすめします。(例「愛犬の名前と家に迎えた日の西暦」など)
デジタル終活についての動画を公開していますので是非ご覧ください。
4.医療・介護の意思表示
介護・医療の方針・延命治療・臓器提供といった、医療や介護に関する意思表示を明確に残しておきましょう。
認知症や病気やケガなどで意思表示が困難な状態になった際に、どのような治療や介護を希望するのか、また危篤状態になった場合に延命治療を希望するのか、臓器提供を考えているかなどを記載しておきます。その他、アレルギーや持病の有無などの記載があれば治療にまつわるアクシデントを防ぐことができるでしょう。
これらの項目は、自分の意思と家族の意思をすり合わせるためにも、事前に話し合っておくとより安心です。
医療・介護の記入ポイント
5.葬儀・お墓についての意思表示
葬儀の形式や予算、お墓の場所は本人の意思として決定しておくことで、家族間のいさかいなく円満に進めることができるでしょう。
通常、葬儀は亡くなってから1〜3日後に決定するのが一般的であり、残された家族は心の整理がつかないまま葬儀という金銭面にも大きな決断をしなくてはなりません。これにはかなりのストレスを感じる方も多いでしょう。こうした家族の負担を軽減するためにも、自分の希望をしっかりと残しておくことが重要です。
「葬儀は質素で家族のみ」「供花や遺影にお金を掛けず、残った家族の生活を優先」といった自分の希望をエンディングノートに意思を残しておくと、残された家族が判断に迷うことなくスムーズかつストレスなく対応できるでしょう。
最近では葬儀の生前予約を受け付けるサービスがあり、生きているうちに葬儀の予約をしておくことで、葬儀社の比較や葬儀費用の検討が可能です。葬儀費用を事前に知っておくことや、家族間で葬儀の規模を話し合っておくことで、万が一の際に心残りが無くなるでしょう。お墓についても事前に用意しておける「生前墓」というものがありますので、死後にかかるお金について知っておいて損はありません。
葬儀・お墓についての意思表示のポイント
6.友人や知人、関係者リスト
友人やお世話になった人に自分の訃報を知らせてほしい場合、エンディングノートに連絡先リストを作っておきましょう。
リストには連絡先に加え、「同年代の友人」「お世話になった取引先」といった自分との関係性を簡潔にメモしておくと役立ちます。
友人や知人、関係者リスト作成のポイント
7.家族や友人へのメッセージ
家族や友人それぞれに、これまで直接言えなかったことやメッセージを残しておくとよいでしょう。面と向かって言えないことが、不思議と文章なら書けるということもあります。
メッセージと合わせて、写真や動画、思い出の品といったものも残しておくのもおすすめです。
大事な情報がつまったエンディングノートの保管は重要です
エンディングノートには重要な個人情報を記入していることから、取り扱いには十分注意しましょう。自宅で保管する方は一見してわからない場所に隠したり、紛失していないかを定期的に確かめ、出来ることなら金庫など鍵のかかる場所に保管するなど工夫することが大事です。
そしてその隠し場所を信頼できる家族のみに伝えておき、万が一の際に読んでもらえるようにしておきましょう。
終活で身の回りを整理したいならリユース相談本舗へ
リユース相談本舗は、使わなくなったものやなくても困らないものを整理・処分したい方に向けた不用品整理のサービスの相談窓口を行っております。売却できるような価値あるものはもちろん買取対応させていただきます。
リユース相談本舗は買取店をベースに運営しているため、一般的な不用品回収サービスに比べて買取対応できる種類が豊富であることが特徴です。
処分したいとお考えのものの中から価値あるものを発見・売却し、処分品の総量を減らしたことで回収費用が削減可能。価格面やニーズ面で希望に沿った不用品回収業者を見積もり提案いたします。
業界初の不用品相談の実店舗を構え、窓口で直接相談することが可能ですので、小さな悩み事や困りごとはすべてご相談ください!