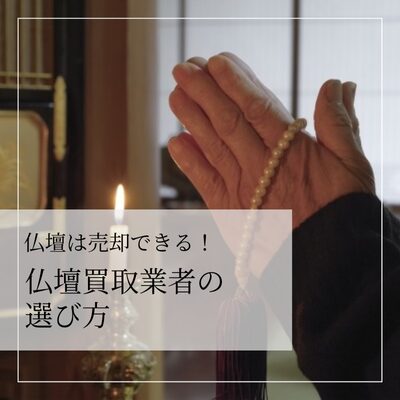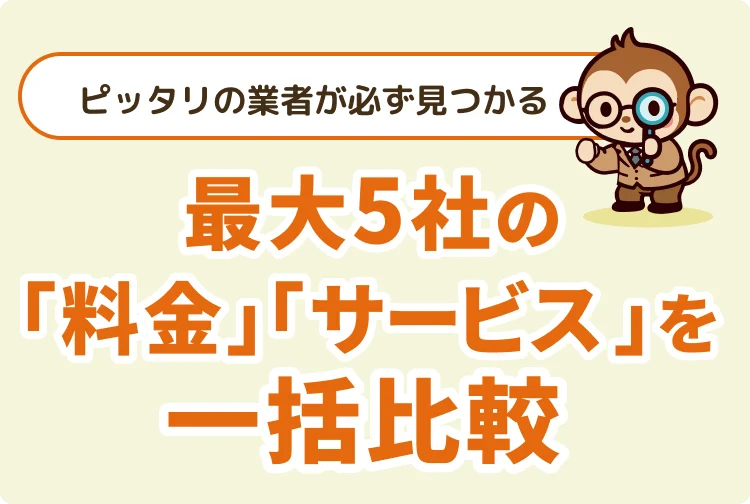位牌は無料で処分できる?仏壇処分後の位牌の供養やお焚き上げの費用

- 位牌とは
- 位牌処分は無料でできる?
- 位牌を処分するタイミングと弔い上げ
- お位牌の処分の仕方について
- 自分で閉眼供養・魂抜きはできる?
- 位牌はどこで処分できるのか
- 位牌処分時の費用・お布施
- 位牌処分の実際の流れ
- 仏壇を処分しても位牌を残すのは可能?
- 位牌の修理・補修とお手入れ方法
- まとめ
- 費用が一切かからない
- 手続きが簡単
- 供養をせずにごみとして処分してしまうことで、後から後悔する可能性がある
- 親族から理解を得られない可能性がある
- 引っ越しや住み替えにより、仏壇や供養スペースが確保できなくなったとき
- 経年劣化により古くなった位牌を新しく作り直すとき
- 仏壇を処分するタイミングにあわせて
- 遺品整理や実家じまいの一環として
- 法要を終えて供養を締めくくる「弔い上げ(とむらいあげ)」の際
- 三十三回忌(さんじゅうさんかいき)
亡くなってから32年後に行われる法要で、関東地方を中心に最も一般的な弔い上げのタイミングとなっています。 - 五十回忌(ごじっかいき)
亡くなってから49年後に行われる法要で、関西地方を中心に広く行われています。 - お寺(菩提寺):閉眼供養も一緒に依頼できます
- 神社:神道に基づく供養の場合のみ対応(仏式とは異なる)
- 仏壇・仏具店:仏具の専門店が処分や供養に対応していることも
- 葬儀社:閉眼供養・お焚き上げをオプションで実施している場合あり
- 遺品整理業者:僧侶と提携して、供養付きで引き取ってくれる業者も多数
- 霊園:永代供養付きの施設では位牌の納骨・供養も可能
- お寺などでお焚き上げをしてもらう
- 合同供養塔などで供養してもらう
- 供養後の位牌はすでに「物」になっているため、自宅で保管することも、燃えるごみとして処分することも可能です。
- 仏壇を置くスペースがない
- 実家と離れて暮らしている
- 継承者がいないけれど供養を続けたい
- 手元に位牌を置いておきたいが、シンプルにしたい
- 表面の軽い傷や汚れ
- 金箔の一部剥がれ
- 塗装の色褪せ
- 読める程度の文字の薄れ
- 構造には影響がない小さな欠け
- 柔らかい布(マイクロファイバーなど)で優しく拭くなど定期的な埃払いをする
- 高湿度は木材の変形や金具の錆びの原因になるため、湿度60%以下を保つ
- 色褪せの原因になる直射日光は避ける
- 素手で触れることで油分が付着するため、触る必要がある場合は白手袋を使用する
仏壇を処分したあと、多くの方が悩まれるのが「位牌の扱いはどうすればいいの?」という点です。
仏壇は手放したけれど、位牌だけが手元に残り、そのままにしていてよいのか、処分しても問題ないのか、不安に感じる方は少なくありません。
また、処分する際の費用や方法など、わからないことが多いのも位牌の処分の特徴です。
そこでこの記事では、位牌の基本的な意味や役割から、正しい処分方法や費用、弔い上げ(魂抜き)のタイミング、さらには位牌の修理・補修といった選択肢まで、初めての方にも分かりやすく丁寧に解説します。
仏壇を処分したあとでも、後悔のない形で位牌と向き合えるよう、ぜひ参考にしてください。
位牌とは

位牌(いはい)とは、亡くなった方の戒名(かいみょう)や法名、没年月日などを記した木製の札や板です。
故人の霊を象徴する存在として、仏教の供養において重要な役割を果たします。
主な種類
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| 白木位牌(しらきいはい) | 葬儀から四十九日までの間に使用する仮の位牌 |
| 本位牌 | 四十九日以降に使用する正式な位牌。黒檀や紫檀などの高級木材を使用する |
| 夫婦位牌・連名位牌 | 一つの位牌に夫婦など複数人の戒名を記したもの |
| 過去帳 | 位牌を使わない宗派や、先祖の位牌が多い場合にまとめて記録するもの |
浄土真宗には位牌がない!?

浄土宗、曹洞宗、真言宗など多くの仏教宗派では、故人を偲ぶために位牌を用います。
一方、浄土真宗では「故人は亡くなるとすぐに仏になる」という教えがあるため位牌を用いません。その代わりに、故人の法名を記した法名軸(掛け軸)や過去帳を安置するのが一般的です。
位牌処分は無料でできる?

結論から言うと、無料で処分することは可能です。
この後に詳しく説明する、閉眼供養やお焚き上げを行う場合は費用がかかりますが、これらの儀式を行わない場合は、位牌を自治体で可燃ごみとして無料で処分できます。
位牌を無料で処分するメリット・デメリット
メリット
デメリット
経済的な理由で費用をかけられない方や、宗教的な儀式にこだわらない方、すでに心の整理がついている方にとっては、無料処分も十分に検討できる選択肢といえます。
位牌を処分するタイミングと弔い上げ
位牌の処分を考えるタイミングは、人それぞれの生活や供養の節目によって異なります。
以下のようなケースで、位牌の扱いについて見直す方が多く見られます。
弔い上げとは
弔い上げとは、故人の供養を一区切りとする儀式で、これ以降は個別の法要を行わず、年忌法要から「祥月命日」や「彼岸・盆」の供養へと移行するものです。
このタイミングで、位牌の処分を検討するかたも多いのではないでしょうか。
主な弔い上げのタイミング
弔い上げのタイミングは地域や宗派によっても異なるので、悩んだ時はお寺や専門業者に相談しましょう。
お位牌の処分の仕方について
ここでは、位牌を処分するための流れや方法について、わかりやすく解説します。
Step1.位牌の処分の前には「閉眼供養・魂抜き」
位牌は「ただの木の板」ではなく、故人の魂が宿っているとされる存在です。
そのため、処分の前には閉眼供養・魂抜きなどの儀式を行い、魂を抜いてから処分する必要があります。
閉眼供養・魂抜きを行うことで、位牌は「物」となり、正式に処分することが可能になります。
Step2.お位牌の処分方法
閉眼供養の後、位牌は以下の方法で処分することができます。
お焚き上げ

位牌を火で清め、魂を天へ還す儀式です。
感謝と敬意を込めて供養しながらお別れできる、最も伝統的で一般的な処分方法です。
永代供養(位牌供養塔)
寺院や霊園に位牌を納めて、維持・管理や供養を代行してもらう方法です。
ただし、「永代」は「永遠」という意味ではではなく、お寺によって供養の期間は異なります。契約期間が終了すれば、自動的にお焚き上げによる処分が行われることが一般的です。
可燃ごみとして処分
閉眼供養(魂抜き)が済んでいる位牌は、宗教的な意味を持たない「ただの物」として扱うことが可能になります。
そのため、素材が木製であれば、自治体の分別ルールに従って可燃ごみとして処分することができます。
また、直接ごみに出すことに抵抗がある方は、白い布や紙に包んでから処分することで、心理的な負担を和らげることもできます。
自分で閉眼供養・魂抜きはできる?

位牌の閉眼供養(魂抜き)は自分で行うことはできません。
位牌には故人の魂が宿っているとされるため、宗教的な作法に則って僧侶にお願いして行うのが一般的です。
自分で閉眼供養・魂抜きをするのはなぜNGなのか?
宗教的な作法がある
魂抜きには読経や作法が必要で、宗派によって形式が異なります。素人では正確な手順が取れない可能性があります。
トラブルや後悔を防ぐ
僧侶の読経があることで、「しっかりと供養できた」という安心感につながります。
自分でしてしまうことで、後になって「本当にこれでよかったのか…」と気に病む可能性もあるため、専門家に任せることをおすすめします。
位牌の閉眼供養はどこへ依頼すればいい?
これまでお世話になっているお菩提寺に相談しましょう。故人の宗派や戒名を把握してくれているため、安心してお任せできます。
菩提寺がない場合は、近所のお寺や、仏壇店・不用品回収業者などの仏壇や位牌の回収と同時に、僧侶による供養を代行してくれるサービスを行っている業者に相談するのがおすすめです。
位牌はどこで処分できるのか
閉眼供養を終えた位牌は、以下の施設や業者で受け入れてもらえます。
リユース相談本舗では、供養前の位牌でも回収させていただきます。
供養にも対応できる、信頼できる仏具回収業者をご紹介いたしますので、安心して位牌の処分をお任せいただけます。
手間や時間をかけず、けれどしっかりとお別れをしたい方は、ぜひリユース相談本舗へご相談ください。
>>リユース相談本舗で位牌処分を相談する
位牌処分時の費用・お布施
実際に位牌の処分をする際、どのくらいの費用が必要になってくるのか、主な依頼先ごとの費用の目安をご紹介します。
※横にスクロールできます| 処分先 | プラン | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| お寺 | 閉眼供養+お焚き上げ | 1万円~5万円 | |
| 神社 | 御祈祷+お焚き上げ | 1万円~5万円 | 神道では仏教の「魂抜き」ではなく、「お祓い」や「お性根抜き」の考え方となります。 |
| 仏壇・仏具店 葬儀社 | お焚き上げ 供養+お焚き上げ | 3,000円程度 5,000円〜3万円 | |
| 遺品整理業者 | 供養+回収 | 数千円〜3万円 | 業者によっては閉眼供養の読経を含まない「回収のみ」の場合もあるため、供養の有無は必ず確認が必要です。 |
| 可燃ごみ | 0円 | 供養をしない、または済ませていれば0円(無料)で処分可能です。 |
最近では、閉眼供養+お焚き上げ+回収をセットで行う不用品回収業者や仏壇処分業者も増えており、個別に依頼するよりもまとめて依頼した方が費用を抑えられるケースもあります。
リユース相談本舗では、位牌の処分について、お客様一人ひとりに合ったプランをご提案しております。
大切な位牌だからこそ、じっくり悩み、後悔のない形でお別れできるよう、心を込めてお手伝いいたします。ぜひ当店へご相談ください。
>>リユース相談本舗の相談カウンターをチェック
位牌処分の実際の流れ
1.現状の確認

位牌が何柱あるかを確認し、誰の位牌なのか、いつのものかをできる限り把握します。また、菩提寺があるかどうかも確認しておきましょう。
2.親族で方針を話し合う
どの位牌を残すのか、どの位牌をまとめるのかを相談します。
先祖代々の位牌を一つにまとめる(繰出し位牌にする)という選択肢もあります。
3.菩提寺またはお寺・仏具店などに相談
位牌の「魂抜き(閉眼供養)」を依頼します。
位牌を残す場合は、新しい位牌の作成や文字入れなども、あわせて相談しましょう。
リユース相談本舗がご紹介する回収業者では、供養・回収を一括で行うことができるので、お客様にかかる負担が最小限でお別れをすることが可能です。もちろんお焚き上げまでしっかり対応させていただきます。
4.魂抜き(閉眼供養)をしてもらう

僧侶に読経をしていただき、位牌の魂を抜いてもらいます。自宅で行う場合もあれば、お寺で行うこともあります。
5.供養済み位牌の処分
6.(必要に応じて)新しい位牌を用意する
残したい位牌がある場合や、複数の位牌を一つにまとめたい場合、またはすべてを処分してしまうことに気持ちの整理がつかない場合には、「繰出し位牌」や「過去帳」の作成をおすすめします。
仏壇を処分しても位牌を残すのは可能?
仏壇処分のタイミングで、必ずしも仏壇と位牌をセットで処分する必要はありません。
チェストや棚の上やサイドボードの一角などに、新たに小さな供養スペースを設けるだけでも問題ありません。
他にも、仏壇のみを処分し位牌は残しておく選択肢もあるので、一部ご紹介していきます。
先祖代々の位牌をまとめる
代々の位牌が増えすぎてしまい、スペースや管理が難しい場合には、複数の位牌をひとつにまとめる「位牌まとめ」や「繰り出し位牌」という選択肢もあります。
この際は、閉眼供養(魂抜き)をした上で、新しい位牌に情報を写し、古い位牌はお焚き上げで処分します。
デジタル位牌という新しい選択肢
現代のライフスタイルに合わせた新たな供養の形として、「デジタル位牌」という選択肢も登場しています。
デジタル位牌とは?
デジタル位牌とは、タブレットや専用ディスプレイなどに故人の名前や写真、法名(戒名)などを表示する新しいタイプの位牌です。
アプリを通じて故人の命日や法要の通知を受け取れたり、ご家族のスマホやパソコンから遠隔でお参りができる機能がついているものもあります。
デジタル位牌がおすすめの人
上記のような、形式にとらわれず、故人を大切に思う気持ちを自分なりの形で持ちたい方に選ばれています。
近年では、手元供養という形で位牌だけを小さなスペースに安置する方法も増えています。
ミニ仏壇やインテリア仏壇に納めたり、棚の一角にコンパクトに設置したりすることも可能です。
位牌の修理・補修とお手入れ方法
長年祀られているうちに傷みや色あせが出てき、処分や買い替えを検討される方も多いかもしれませんが、実は位牌の修繕をする方法もあります。
修理や補修を行うことで再び美しく、安心してお祀りすることができます。
修理が可能かどうかの判断基準
以下のような症状は修理・補修が可能なケースがあります。
位牌の修理はどこに依頼する?
仏壇仏具店
多くの仏具店で修理サービスを提供。お店によっては見積もり無料のところも
漆塗り職人
漆塗りや金箔の修復が必要な場合
宗教用具修復専門業者
位牌を含む宗教用具の修復を専門とする業者
菩提寺
直接修理はしなくても、信頼できる業者を紹介してくれることがある
自分でできる位牌のお手入れ
思い入れのある大切な位牌だからこそ、同じものを長く、美しい状態で祀り続けるためには、日ごろのお手入れがとても大切です。
日常的なお手入れポイント
まとめ
位牌の処分は、故人への感謝と敬意を込めて行うべき大切な儀式です。費用面については、閉眼供養やお焚き上げを行わない場合、可燃ごみとして無料で処分することも可能です。
ただし、無料で処分できるとはいえ、供養を行わないことで後から後悔する可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。
供養を行う場合の費用は依頼先によって異なり、お寺での閉眼供養とお焚き上げで1万円〜5万円程度、遺品整理業者や仏具店では数千円〜3万円程度が目安です。
最近では供養と処分をまとめて依頼できる業者も増えており、費用を抑えられるケースがあります。
位牌を処分する際は、閉眼供養(魂抜き)を行った後、お焚き上げや永代供養といった方法で処分するのが一般的です。
弔い上げのタイミングは宗派や地域によって異なりますが、故人が先祖の仲間入りをしたと考える大切な節目です。
また、仏壇を処分しても位牌のみ残しておくことが可能です。
故人や家族の気持ち、親族の理解なども考慮しながら、最適な方法を選びましょう。